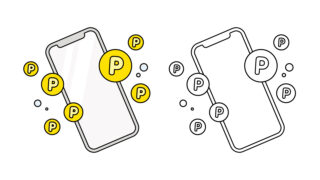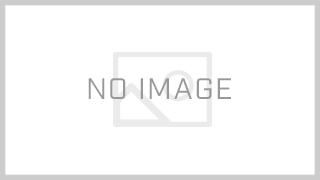「投資は怖いから、全部貯金にしている」──そんな風に思っていませんか?
ですが実は、「貯金だけ」という選択も、立派な“投資判断”のひとつです。
本記事では、投資初心者の方に向けて「貯金という投資」の正体を明らかにしつつ、デフレ・インフレといった経済環境との関係、そして現代における資産防衛の考え方を解説します。
1. 投資と貯金の本当の違い
| 項目 | 投資 | 貯金 |
|---|---|---|
| 目的 | 資産を増やす | 資産を守る |
| リスク | 値動きがある | 元本保証(名目上) |
| リターン | 高い可能性あり | 極めて低い(0.001~0.1%) |
一見、貯金は「リスクのない安全な選択」のように見えます。
ですが、その実態は『円建て資産への全額投資』です。
2. 「貯金=日本円にフルベットしている」状態
私たちが銀行にお金を預けているとき、それは日本円という通貨資産に全額投資している状態です。
これはつまり、次のようなリスクを抱えていることを意味します:
- 円安:外国通貨に対して円の価値が下がる → 輸入物価上昇で生活コスト増
- インフレ:モノの値段が上がる → 貯金では購買力を維持できない
- ゼロ金利:銀行に預けてもほとんど利息がつかない
「円の価値が未来永劫保たれる」と信じて、100%を賭けている。
それが“貯金”の正体なのです。
3. デフレのとき、貯金はむしろ有利
貯金という投資が効果的に働くのは、デフレという状態です。
デフレとは、物価が持続的に下がっていく経済状態のことです。
この場合、現金の価値は相対的に上がるため、貯金しているだけで購買力が増します。
例えば、昨年100円だったパンが、デフレにより今年は 90円に値下がりしたとしましょう。その場合、同じ1万円で去年は100個買えたところ、今年は111個と11個多くのパンが買えます。
実際、1995〜2012年ごろの日本では、物価が停滞・下落しており、現金を持っていることが安全資産とされていました。
つまり、デフレ下では「貯金」こそが強い投資戦略となり得たのです。
4. インフレ時代には、貯金は“確実に損をする投資”になる
現代の日本では、エネルギー価格や食品価格の上昇を中心に、明らかにインフレの時代が到来しています。
仮にインフレ率が年2%で推移した場合、100万円の貯金は10年後には 約82万円分の価値となります。物価上昇に追いつけないまま、資産は実質的に目減りします。
つまり、「貯金だけ」の戦略は、インフレ時代においてはリスクが非常に高い選択肢なのです。
5.通貨以外の資産も保有しよう
「投資は怖い」と思っている方ほど、“円以外の資産”という選択肢を持つことが重要です。
具体的な方法としては下記の通りです、
- 株式、債券、不動産、金などの実物資産を一部でもポートフォリオに組み込む
- 外貨建て資産(米ドル債券、海外ETFなど)を活用することで通貨リスクを分散
- 積立NISAやiDeCoなどを活用して、長期・積立・分散を実践する
こうした行動が、インフレや円安、経済変動への具体的な備えになります。
こうした分散戦略こそが、インフレ・円安・地政学リスクへの現実的な備えになります。
6. 初心者が今日からできる3つのステップ
① 生活防衛資金(3〜6ヶ月分)を確保する
まずは、病気や失業などの不測の事態に備えて、生活費の3〜6ヶ月分は現金で保有しましょう。
この資金は投資には回さず、銀行預金などのすぐ使える形で確保しておくのが原則です。

② 投資の目的を明確にする
「何のために投資するのか?」を明確にすることで、リスクの許容度や運用期間も決まります。 たとえば:
- 老後資金(20年〜30年運用)
- 子どもの教育資金(10年程度)
- マイホーム購入資金(数年〜10年)
目的によって、選ぶべき資産クラスやリスクの取り方も異なります。
③ 少額から積立投資を始める
初心者におすすめなのが、「積立NISA」や「iDeCo」などの少額からの長期投資制度です。
特に積立NISAは、運用益が非課税になるため、長期で資産を増やすには非常に有効な制度です。
結論|「貯金=安全」は時代遅れ?
デフレの時代が終わりを迎え「貯金しておく=リスクがない」という状態はもはや成り立たない状態となってきています。
「貯金する」という行為の選択こそ“日本円にフルベットした高リスクな投資”であることを、私たちは自覚すべきです。
まずは少額から、知識をつけながら一歩を踏み出してみましょう。